近年、世間では、働き方改革が叫ばれています。既存の人事制度に課題を感じ、人事制度の改定を検討している経営者の方々も多いのではないでしょうか。
今回のブログが、そのような経営者の方々の考えの助けになればと思います。
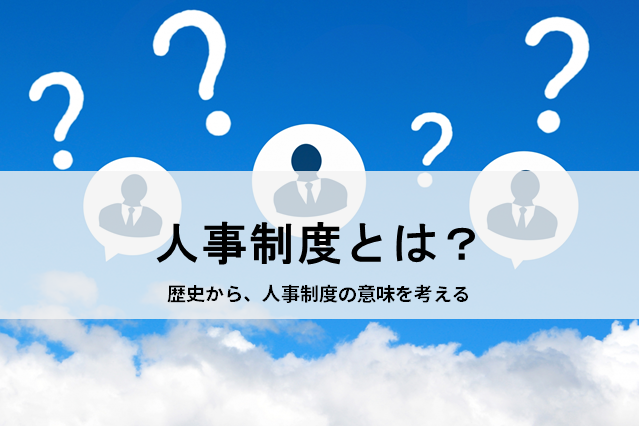
人事制度とは?
まず始めに、何故、会社には人事制度が必要なのでしょうか?
言い換えると、人事制度の目的とは何でしょうか?
人事制度の“制度”の説明は、たくさんの情報が流れています。しかし、こと“ヒトごと(人事)”に焦点を当てた説明は少ないように思います。
そこで今回、この人事制度の目的を考えるために、人事制度の歴史を紐解きたいと思います。
人事制度の歴史
江戸時代:生活基盤を保障する雇用制度
交通手段が少ない江戸時代には、奉公人という住み込みによる労働が主流でした。この雇用形態では、貨幣的な報酬はわずかな小遣いを除けば、雇用期間中に直接支払われることはありませんでした。
これは、店に住み込んで労働する代わりに、衣食住に渡って面倒を見てもらうという、生活基盤を保障してもらう雇用制度です。
この時代の人事制度(雇用制度)の目的は、雇われる側から見ると、物質的な生活保障であったと言えます。
明治時代:労働の対価としての賃金制度
明治時代に繊維産業の工場地帯が発展し始めると、従来の住み込みの型の雇用ではなく、通いによる雇用形態が主流となります。
そして、従来の期間雇いが普通であった雇用形態から、日雇いによる雇用形態も登場し始めます。これが「長期雇用の奉公人型」と「短期雇用の職人型」との2種の雇用形態の登場です。
そして、日本の労働基準の原型となっていくのが、この「奉公人型」や「職人型」を含む工場労働者(職工)です。つまり、明治時代に、工場という場を通じて人事制度の基礎が造られ始めます。
具体的には、1879年(明治12年)に渋沢栄一の呼びかけによって大阪紡績が株式会社として設立されると、日清戦争・日露戦争後の株式ブームを経て、会社制度が定着してきます。これにより、株式会社と工場制度が一体となって、賃金制度が考えられるようになります。
そして、工場では職工の労働に対する報酬が賃金という形で、直接雇われる者に支払われるようになります。
同時に、この明治時代に、民法でも雇用契約のあり方を「労働に従事すること」と「報酬を支払うこと」の債権契約と定められることになります。
この時代の人事制度(賃金制度)の目的は、労働の対価として報酬が貨幣として支払われること。すなわち賃金の概念が広がることでした。

昭和前期:生活を支える生活給制度
大正期には、1914年(大正3年)に始まった第一次世界大戦中の生産活発化から熟練の職工の不足が深刻化します。さらに、物価が急騰し、大戦後の不況や労働運動の活発化が見られました。
こうした影響もあり、新卒を採用し企業内で職工を養成する基幹工を確保する動きが勧められます。また、物価上昇には物価手当や臨時手当などの支給や臨時昇給があり、労働移動を防止し定着を勧めるための勤続手当や勤続を反映した昇給も認められるようになります。
このように大正期には、現代でいう福利厚生とみられる各種手当が設定され、賃金体系が複雑化していきます。この流れの中で、日本の賃金の重要な特色である生活給の思想が始まります。
昭和時代に入り、1929年(昭和4年)のアメリカで起きた世界恐慌の影響により、日本経済も危機的状況を極めました。こうした中、賃金制度の面では、昇給停止、諸手当削減、賃金切下げなど人件費削減策が推進されるようになります。
そして、1931年(昭和6年)に満州事変が始まり、経済社会は戦時体制に入ると共に、経済統制が進められました。賃金面でも、インフレ抑制の観点から政府が賃金統制に乗り出しました。これが日本企業の賃金制度に大きく影響を与えることになります。
具体的には、政府は生活給の推進に乗り出し「賃金は労務者及びその家族の生活を恒常的に確保すると共に勤労業績に応ずる報償たるべきもの」と定義付けました。企業側も賃金のあり方として、生産奨励と同時に生活保障の要素が重要であることを指摘し、政府と企業側が同調しています。
この政府と企業側との一連の動きは、家族を抱えて生活費の高まる中高年労働者に対して賃金を高くすることにより生活安定を図り、戦時経済体制下で生産活動の円滑な推進を図ったのでした。
この流れは、昭和の戦後に確立します。つまり、この時代の人事制度(生活給制度)目的は、雇われる側の立場の生活を賃金によって保障すること。すなわち、生活給が浸透することでした。
昭和後期:生活給と職務給との融合による職能給制度
しかし、1950年(昭和25年)頃に経済が安定し出すと、この生活を軸とした生活給制度に対する見直しが始まります。すなわち、経済活動、技術水準などの面で格段に進んでいたアメリカから、職務給制度の導入が賃金制度の合理化につながるとして経営者側から主張されるようになります。
職務給制度とは、仕事内容に応じて、社員を区分して等級別に評価し、この等級に応じて、賃金を決定する制度です。
ところが、当時の生活給制度は、年齢、家族数、勤続年数の個々の労働者の従事する労働内容とは直接的には関係のない属人的要素で賃金が決まっていました。このため、賃金を労働の質と量に応じて決定する職務給制度のアメリカ的人事管理の考え方とは相いれないものでした。
そこで考え出された制度が、職務遂行能力を基礎とする職能給という考え方です。
これは職務給と生活給の両者の性格を保有しており、いわば両者の折衷案と言えます。職能給は、職務給制度の賃金の頭打ちを回避しつつ、より柔軟な配置そして労働者の能力開発を促進するという性質をもつことから、職務給に代わるものとして、国内で評価されるに至りました。
この結果、1965年以降、職能給が次第に広まって行きます。そして、1990年代には各種産業の賃金政策では「基本給=生活給+職能給」が掲げられるようになります。
しかし、職能資格制度や職能給の実務上の経験を積み重ねるにつれて、下記のような色々な問題が発生してきます。
- 運用が年功的
- 発揮能力に応じた昇格・降格ができない
- 高資格化による人件費の高騰
- 職能資格の定義や基準から実態から乖離
- 職能要件の有名無実化
この時代の人事制度(職能給制度)の目的は、雇われる側の生活を保障する生活給と、企業として雇う側が求める職務遂行能力とを総合的に評価することでした。

平成時代:成果主義への傾倒から発展した役割給制度
1990年代初めには、バブル経済の崩壊、冷戦構造の崩壊と社会主義諸国の市場経済化、経済のグローバル化の進展により、それまでの右肩上がりの日本経済や企業経営が期待できない状態に至りました。
年功的な運用なっていた職能給の見直し
その時代の変化が、成果主義賃金への意向を促す契機となったのです。特に「非世帯主の従業員の増大」が成果主義への動きを強めています。
つまり、男性では未婚者が増加しています。また、女性従業員も増加しており、女性の多くは非世帯主です。従って、従業員全体の中での非世帯主の割合が高くなる傾向にあります。
そして、生活給と生活保障的賃金は表裏の関係にあります。つまり、生活保障的要素は世帯主である男性中高年にとっては好ましいですが、非世帯主の立場からすると世帯主ほどには年功的な生活給を必要としないし、強く望みません。
結果として「非世帯主の従業員増大」が賃金の年功性を弱め、能力主義的性格、成果主義的性格を強める方向に作用しました。
また、企業業績の低迷が、人件費の削減策として、成果主義賃金を推進した面があります。
更に、コーポレート・ガバナンスの変化も挙げられます。すなわち、コーポレート・ガバナンスとは企業統治と訳されますが、上場企業の主要株主が、それまでの金融機関や取引先から機関投資家に変化しつつあり、経営側が企業業績や株価動向に過敏に反応しなければならなくなったのです。
このため、企業業績の向上には人件費の効果的活用が求められるようになりました。
新たな役割給という概念の登場
そして、成果主義賃金の広がりとともに職務給が再び広がりを見せつつあります。しかし、1950年代、1960年代に一度検討された職務給とは異なります。
それが「役割」という新しい概念です。職責等級や役割等級という名称で表現されることもあります。
この制度の内容は、一般社員層においては、企業が立てた目標達成に貢献するような能力を序列化し、専門性の発揮の程度に基づき社員を序列化します。
能力の要素を残しつつ、管理職層においては社内のポストが格付け基準の全面に出ています。仕事基準の職務等級制度と人基準の職能資格制度の折衷案とも言えます。
この時代の人事制度(成果主義・役割給制度)の目的は、雇われる側に立った生活給を縮小させるために、企業側の立場で、より明確な事業への貢献度が重視されることでした。
まとめ
このように、時代背景にとともに人事制度は常に変化しています。また、あくまでも日本全体の人事制度の傾向を示しているため、個別の企業では事情は異なります。
具体的には、現代においても年功序列の年功給が採用されている企業も存在します。また小さい企業になると、賃金制度と言える程の賃金体系が確立されておらず、社員毎に社長の感覚で給与決定している企業も多いのではないでしょうか。
人事制度には、経営と同様に唯一の正解はありません。人事制度の在り方も経営者の自由です。
今後、あなたの会社が人事制度の導入や改定を考えた場合、時代の流れに沿うことは一つの考えではあります。
しかし、私が人事制度を考える上で、大切にして頂きたいことは、まずは人事制度には正解がないということを理解して頂くことを前提に、上述した人事制度の歴史毎の目的に加えて、その本来の意味について理解して頂くことです。
関連ブログ「人事制度の普遍的な目的とは」では、時代毎の人事制度の目的から見えてくる、その意味について解説しています。続けてお読み頂ければと思います。